江戸時代の新潟の様子を伝える「正保越後国絵図」。
●新発田市立図書館所蔵(新潟県指定文化財) ●写真提供:新潟県立歴史博物館
信濃川と阿賀野川、そしてその2つを結ぶ小阿賀野川に囲まれた地域は、かつて「亀田郷」と呼ばれ、胸までつかる泥田だった。
この一帯を人々は「芦沼」「地図にない湖」とも表した。
『新潟=新しい潟』が、みずみずしい稲穂たなびく米どころになるまでの、先人の想像を絶する苦闘『水と土の歴史』を振り返る。
信濃川と阿賀野川に
囲まれた『新しい潟』
「丸潟(まるがた)」「長潟(ながた)」「三枚潟(さんまいがた)」「鍋潟(なべがた)」…新潟市には、今も「潟」が付く地名が多く残っている。市の南部には「新津(にいつ)」や「袋津(ふくろづ)」「覚路津(かくろづ)」「木津(きつ)」など港を意味する「津」の付く地名もあり、かつてここに港があったことを伝えている。
新潟市中心部を空から眺めると、この土地が『新潟=新しい潟』と呼ばれた理由が見えてくる。四方を日本海、信濃川、阿賀野川、そして、2つの大河を結ぶ小阿賀野川に囲まれた巨大な中州のような地形。そのうち約3分の2は海抜0メートル以下である。むかしは満潮時になれば海の底に沈んだ地域なのだろう。それが、信濃川や阿賀野川の流れによって土砂が運ばれ、自然と「オカ」になったのだ。
新潟県は、カロリーベースでの食糧自給率が102%(平成23年度)。全国でもトップクラスの高さを誇り、自他ともに認める米どころだ。夏になると、上越新幹線の車窓からは、緑の絨毯のような美しい田んぼを見ることができる。この田んぼを潤しているのが、信濃川と阿賀野川、それにつながる大小さまざまな支流だ。今では恵みの川に思えるだろうが、「地図にない湖」の時代には気まぐれに氾濫し、あらゆるものを沈めた。稲作にとっては、人知では治めようのない脅威だったのだ。

一歩足を踏み入れると
胸までつかる泥田
かつて、横越、大江山、亀田、両川、曽野木、鳥屋野、山潟、石山、大形の9地区、新潟市の南側一帯は『亀田郷』と呼ばれる泥田だった。信濃川と阿賀野川、小阿賀野川に囲まれた低くて平らな輪中地帯。海抜0メートル以下の低湿地だったことから「地図にない湖」とも呼ばれていた。なみなみと水が溜まった泥田に一歩足を踏み入れれば、ズボッと胸まで一気につかる。芦が生い茂ったその泥田を、人々は『芦沼』と呼んだ。
田んぼには舟で移動した。苗や刈り取った稲を運ぶのも全部舟だった。農家は堀沿いに軒を連ね、玄関前から舟を出して田んぼに通う。
命を失うこともあった
芦沼での稲作作業
清五郎で代々農業を営み、むかしを知る農家は「ここは川や海の水量に影響される田んぼで、潮の満ち引きに左右されながら仕事をしてきた」と言う。
「田に波が立つとあぜが流されて、自分ちの田んぼがどこだか分からなくなってしまう。よく波が立たない『かやあぜ』を作ったもんです」と続けた。『かやあぜ』とは、芦の茎で作ったあぜのことだ。芦の茎が防波堤となって波を防ぎ、稲や泥の流出を防いでくれる。土盛りのあぜと違って水に流されないので田んぼの区画も分かりやすい。
現在はアルビレックス新潟のホームスタジアムである『デンカビッグスワンスタジアム』や新潟市民病院などが次々と建ち並び、新潟市の中心地となりつつあるこの土地も、昭和20年代以前までは、子どもが田んぼの中に立つと口の中に水が入ってくるほどだったそうだ。農作業中にあやまって水に流され、命を失う人もいたという。田植えは乾田よりも遅い6月から7月にかけて行われた。田植えが遅いので収穫の時期も遅い。稲の刈り取りはあられが降る頃まで続いた。秋の彼岸を過ぎると、田んぼの水は身を刺すような冷たさに変わる。そのような泥田での力仕事は、言葉にならないほどのつらさだったことだろう。
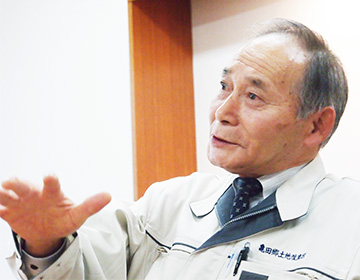
芦沼から緑の美田へ
亀田郷乾田化のあゆみ
亀田郷の歴史は土地改良の積み重ねだ。第1期の土地改造期(昭和16年~34年)は、当時の金額で30億円、反当たり46,000円という巨額の国家予算が投じられた。乾田化が一気に進んだのは、昭和23年に『栗ノ木排水機場』ができてからだ。政府は戦後の食糧増産の場として約1万ヘクタールの亀田郷に目をつけ、東洋一の排水機場を建設し、乾田化を急いだのだ。昭和26年には『亀田郷土地改良区』が発足。『芦沼』と呼ばれた亀田郷が今の姿になったのは昭和33年頃だ。

亀田郷土地改良区の理事長、山我森實さんは言う。「私が生まれたのは昭和19年。子ども時代は終戦後間もなく、最も物資がなかった。都会からも食料を求めて多くの人が疎開に来ていました。目の前の水と戦い、自分たちで米を作らなければ食べるものがない。必死だった。そして、先人たちは強かった」。逆境にあったからこそ、強く、大きな夢を持つ佐野藤三郎氏のようなカリスマも生まれた。夢を追う人が出なければ時代は進まない。
乾田化が進むにつれて、荷運びの道具は舟からトロッコ、一輪車に変わり、田おこしも手作業から牛耕に変わった。昭和33年以降になると、耕運機や田植機が導入され、農薬や除草剤なども出始める。昭和39年の新潟地震で被害を受けた栗ノ木排水機場に代わって昭和43年に親松排水機場が稼働すると、圃場整備はさらに進み、亀田郷の土地改良の目的は、乾田化から生産性アップと多角化経営に変化していった。

新潟市の雨は
どこに溜まるのか?
ところで、新潟市の雨はどこに溜まるのかご存知だろうか?
答えは鳥屋野潟だ。鳥屋野潟の水面は海抜マイナス2・5メートルと新潟市で最も低い土地になる。雨は新潟市内に張り巡らされた農業用の用水路を伝って鳥屋野潟に注ぎ、親松排水機場のポンプで信濃川に排出される。万が一、この親松排水機場のポンプが止まって鳥屋野潟がいっぱいになると、あふれかえった水が低い土地に溜まり、亀田郷は「地図にない湖」になってしまうのだ。
実際に、昭和39年の新潟地震で栗ノ木排水機場の機能が低下したとき、亀田郷一帯はすぐに水浸しになった。親松排水機場はその栗ノ木排水機場の代わりに造られた排水機場だ。新潟市民の暮らしは、24時間休まず稼働している親松のポンプによって支えられている。ではいったい、どれほどの水が排水されているのだろうか?

新潟の治水の要
親松排水機場
ある日の鳥屋野潟の水位は海抜マイナス2・46メートル。信濃川の水位は海抜0・69メートル。鳥屋野潟と信濃川の高低差は約3メートルだ。親松排水機場は鳥屋野潟の水をポンプでくみ上げ、信濃川に排水しているのだ。全部で4台ある排水ポンプがすべて動くと毎秒60トンの排水が可能になる。毎秒60トンといえば、25メートルのプールを6秒で空にするほどの能力だ。ちなみに昨年の親松排水機場の年間合計排水量は約3億7千万立方メートル。1年間に鳥屋野潟105杯分の水を排水したことになる。3日に1回は鳥屋野潟の水をすべて信濃川に空けていることになるのだ。
数字にすると、いかに新潟は水が溜まりやすい低い土地であるかが分かる。

環境再生への取り組み
丸潟新田のビオトープ
親松排水機場のおかげで、亀田郷は、農作業の機械化や多角化が進み、梅や花卉、女池菜なども栽培できるようになった。しかし、その一方で生態系も変わっている。豊かな生態系を取り戻そうと、亀田土地改良区では環境湿地の再生に取り組んでいる。休耕田を湿地としてよみがえらせることによって、土壌が豊かになり、水質も良くなるという。
丸潟新田の再生湿地に行ってみた。一反ほどの田んぼに、ミズアオイやガマの穂が生い茂っている。かつてこの土地が巨大な湿地だったことの証拠だ。水を張ってから半年で、再生湿地にはギンブナの稚魚や水鳥、野鳥のバンなど、今までに見られなかった生物たちが戻ってきていた。
現在の亀田郷の良さは、まちに近く、自然にも近いことだ。田園と住宅、街が共存している。田んぼが結び目となって、人と自然、地域と地域、命と命をつないでいる。先人たちが数百年をかけて水と闘い、やっと完成させたこの土地を未来にどうつなげていくのか? 土は私たちに問いかけてくる。



